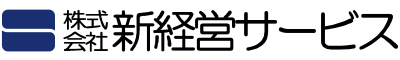バイマンスリーワーズBimonthly Words
心のキャッチボール
新年あけましておめでとうございます。
本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。
~ AIを搭載したロボットに所得税をかける? ~
現場の仕事がAIやロボットに代わり始めているため、
このままだと労働者が納めてきた所得税が減少してしまう。
そこで、AIやロボットに所得税をかけようという考えです。
実際にはロボットを所有する企業が負担することになりますが、
少子高齢化が進む日本では、充分に起こりうるでしょう。
すでにロボットは製造業や物流業、建設業をはじめ、
飲食・医療・農業など幅広い分野で活躍しています。
ところが患者とのコミュニケーションが不可欠な医療従事者や、
人の温かさや信頼関係が必要な介護や保育の仕事はどうか?
人の心の変化に対して臨機応変に対応する高度な仕事が、
AIやロボットが充分にこなせるとは思えません。
人として生きる道を学ぶ仏教の専門家として活躍する、
大峯千日回峰行を成し遂げた 塩沼亮潤大阿闍梨はいう。
「人が幸せになるための行為にAIは何の役にも立ちません。
AIが経済を制しても 人の心は支配できないのです」
ロボットに仕事を移行して大幅に生産性が上がっても、
それが人の幸せにつながるとは限らない、というわけです。
冷え切っていた夫婦仲が 一か月で円満になったわけ
大峯千日回峰行とは、奈良県の吉野山にある金峯山寺から大峯山寺まで、
険しい山道を一日48キロ、16時間かけて千日間歩き続ける荒行。
大阿闍梨とは、この荒行を達成した者だけに与えられる称号で、
大峯山1300年の歴史の中で萬行したのは二人だけです。
塩沼さんは「お寺は生き方の大学」であり、
一に勤行(ごんぎょう)、二に掃除、三に追従(ついしょう)、四に阿呆
のルーティン化されたカリキュラムがあるという。
一の勤行とは、毎朝毎夕の読経などのお勤めのことで、
二の掃除は、身の回りをきちんと整え規律や時間を守ること。
この二つまではなんとかできるが、この先が難しい。
三の追従は、相手が喜ぶことをしなさいという意味で、
好きな人ならいいが、嫌な人を喜ばせるのは心理的に辛い。
四の阿呆はもっと大変で、「おまえ、阿呆やな」と言われても、
「ハイッ!」と答えて、嫌な感情をパッと解き放つことだという。
塩沼さんの話を聞いてから冷え切っていた夫婦の仲が、
一か月で夫婦円満になったというありがたい話があります。
悪化したのは朝に奥さんがゴミ出しを頼んだことに始まります。
夫は「ゴミを出して」と言われるたびにムッとして出していました。
ところが塩沼さんの話を聞いた翌日から「ハイッ!」と返事をし、
次の日もその次の日も「ハイッ!」と明るい口調で応えました。
すると、一週間ほどしたら夕食の献立が豪華になってきて、
一か月したらすっかり夫婦仲が良くなっていたという。
「ハイッ」と返事をするのは簡単なことですが、
嫌なことを言われ、明るく、元気な口調で、
「ハイッ!」と答えるのは至難の業です。
この対応が“追従”といえるでしょう。
相手を喜ばせるには 自分を捨てる訓練が必要
追従の意味を知り「返事は0.2秒」を鉄板ルールにした、
人を惹きつける講演で有名な 中村文昭さんを思い出しました。
修業時代、すぐに返事をしない中村さんに師匠がこう言いました。
「返事の遅いヤツの特徴は、言われたことが自分にとって、
得なことか損なことかを考えとるんや。
損得をいう人間を誰が信用するか!
損得を先に考える人間に、大切なことを任せたいと思うか?!」
ガツーンとやられたその時から、人との接し方が変わります。
「あなたに対してNOはない。YESとハイだけです」
と、開き直って0.2秒で返事をするようにしたら、
自分の都合がどんどん捨てられるようになったという。
それは、自分を捨て、相手を喜ばせる「覚悟」の訓練でした。
私が高校野球の選手だった頃はキャッチャーで、
ベストな投球を組立てることを得意にしていました。
その後、ピッチャーも経験しましたが思い通りにできず、
そこで焦りや不安を感じる、繊細な投手心理に気づいたのです。
「どんな球でも受けてやるから思い切って投げてこい!」
と、なぜ大きな懐で受け止めることができなかったのか…。
ピッチャーの気持ちを考えず、自分が考えた配球を優先する、
なんとわがままなキャッチャーだったのかと反省するばかりです。
「愛」とは「心を受けとる」と書く
リーダーが人を機械や道具のように使う考え方は「操作主義」と呼ばれます。
これは幹部社員が育っていない組織では通用するかも知れませんが、
意識の高い幹部なら人へ敬意を払わないリーダーであることを、
簡単に見抜き、確実に彼らの心は離れてしまいます。
「AI」は、日本語では「愛」になります。
AIには「愛」が理解できないかも知れませんが、
人間が抱える悩みや不安をAIが受け止めてくれたら、
「操作主義」のリーダーよりも頼もしい存在になるでしょう。
人に対する愛をAIに奪われることがないように、
「おまえ、阿呆やなぁ」と言われても、
ニコッと笑って「そうやね」と、
軽く流せる人になりたい。
塩沼氏はいう。
「“愛”という字は“心を受けとる”と書きます。
愛を与え、愛を受けとる“心のキャッチボール”で、
人は幸せを感じるのではないでしょうか」
昨秋、弊社の管理部門で長年貢献してくれたスタッフが病で急逝しました。
自宅に届いたご主人からの喪中ハガキに言葉が添えてありました。
「妻は 御社と皆様が大好きでした」
あれだけ無茶なお願いや苦言を発していたのに、
グッと受けとめてくれていたのだと胸が熱くなりました。
最近は、モノ忘れや単純ミスが増え、
家ではカミさんから叱られることがしばしば。
そこでムッとならず阿呆になれるといいが…これが極めて難しい。
今年も修行は続きます。